「みなさん、楽しむために覚悟を決めて移住するんだから、もう地域を自分の色に染めたら良いんですよ」
快活に笑うのは茨城県神栖(かみす)市にあるお寺の住職、吉本栄昶(えいしょう)さん、43歳だ。
地元のお祭りの復興や、旅行者に神栖市ならではの生活体験を提供する神栖農泊協議会活動など、神栖市の町おこし事業で中心的な役割を担う吉本さんだが、実は神栖市出身ではない。
前の住職が夜逃げした
約20年前、吉本さんは、神栖市の恵日山長照寺(えにちざん ちょうしょうじ)の住職としてこの地に移住してきた。
請われて移住してきた吉本さんだったが、移住してみると、地域の中で自分のお寺のイメージは最悪だった。
前の住職が夜逃げをした後だったからだ。
「何しに来た、いまさら来るんじゃねえ、とか、何ヶ月で辞めるんだ、とかね。お線香投げられたこともありましたね(笑)」
恵日山長照寺は、1747年、神栖地域の開拓のために移転してきたお寺だ。
地域住民の役場機能も兼ねてきた一般的なお寺と違い、檀家さんとの繋がりも比較的薄く、財政基盤の弱いお寺だった。
お寺が経済的に大変だったため、昼は住職としてのお勤めをして、夜はゴルフ練習場のボール拾いなどをしながら、がむしゃらに奮闘する日々が始まった。
「兄が大病で入院していた時期とも重なって、お金は本当にありませんでしたねぇ」明るく振り返る吉本さん。
誰も協力してくれない、知らない環境の中で、投げ出そうとは思わなかったんだろうか。
「当時は、他のお寺の、のほほんとしている坊さんに負けたくなかったんですよね、ベンツに乗っている坊さんとか(笑)。ま、私の住んでいるこのお寺は、今も鍵の閉まらないボロ家ですけど(笑)。」

写真:恵日山長照寺(えにちざん ちょうしょうじ)
失敗続きだった祭りの復活
地域に溶け込め始めたのは一つの契機は、地元の祭りの復活だった。
移住して3年目、地元のおばあちゃんから、20年以上行われていない地域のお祭り“おめこ祭り”をやってほしいと頼まれた。元来、この地の開拓者を供養する大切なお祭りだった。
「思ったらすぐやる人間なもんで、すぐに動きましたが、2年失敗しました」

一年目は、一人でやろうと気負って失敗。
次は“おめこ祭り”という名前を、歴史的に正式な漢字の名前に変えたら、誰も読めずに失敗。
「広島出身の私には、やっぱり名前に抵抗感があったんですね。でもそれはやっぱり今住んでいる地域の感覚を理解し、親しまないといけなかった」
3年目、地元の青年団に声を掛けた。“そういえば、小さい頃そんなお祭りあったな”と、思った以上の協力が得られた。
地域の人たちもまた、何年も無償で懸命に奔走する住職の姿を見ていた。
「あの人頑張ってるよっていうのが伝わりやすいのも、田舎の良さかもしれません」

いまや2日で3,000人が集まるお祭りに
しかし、20年も行われていない祭のための道具も機械もなかった。
連日夜中3時くらいまで、車のライトを頼りにステージを手作業で作りながら、地元の人たちと準備をした。
「人間、疲れ過ぎると笑うんですね。ハイテンションになって」
一人じゃなにもできない。吉本さんは実感した。
年を追う毎に祭の形が整っていき、いまや、2日間で3,000人が訪れる、地元が誇るお祭りになった。
子どもに優しい祭だ。
裕福な家の子どもも、そうでもない子どもも、気兼ねなく祭りを楽しめるように“手伝いをしたら無料”“ゴミを10個拾ったら100円”など、吉本さんが様々な工夫を凝らす。

祭りの他、子ども合宿など多くのイベントで子どもと触れ合う地域だ
「私も役員さんも赤字ですけどね(笑)。でも、そんな祭りが日本に一つくらいあってもいいかなと。自分がやりたいことを突っ走ってやって、そこにやっぱり賛同してくれる人が出てきて、楽しくなりましたね」
かつて“何しに来た”となじられた“貧乏住職”のエネルギッシュな姿勢が、少しずつ受け入れられるようになっていた。
キャベツ泥棒と間違えられた
それでも、20年に渡る奮闘記には、抱腹絶倒のエピソードが次々と出てくる。
6年ほど前に、地元の農家の方から2トントラックにいっぱいのキャベツをもらった。
当時、広島ナンバーだった吉本さんの車で運んでいると、地元の警察に“キャベツ泥棒”と間違えられて、止められた。
荷台に積んだバッグの中の免許証を取り出すため、キャベツをどかすと、畑で使う包丁が3本出てきた。
「これは銃刀法違反だって、大騒動ですよ(笑)。当時、私、神栖警察署協議会の会長もしてたんですけどね。」

写真:吉本栄昶住職
「ああ、喜んでくださってたんだ」
がむしゃらに動き続けた吉本さんは移住10年の節目に、住職を辞めようと思ったことがある。
何気なく檀家さんに話すと、翌日には、本堂の入口に車が横づけされて、吉本さんの車が出られなくなっていた。
「檀家さんたちから、住職に出ていってもらいたくないんだと。別に、次の日いなくなるって話じゃないわと(笑)。迷惑でしたけど、嬉しかったですね。あの頃はがむしゃら過ぎて、住職ありがとうなんて言葉、一回も耳に入らなかったですから。ああ、喜んでくださってたんだと」

写真:地域の人たち
三遊亭圓窓「愚痴をネタに変えたらいい」
その頃だった。
落語家・三遊亭圓窓と出会った。
「辛い経験をした人のほうが、話は面白くなる。愚痴をネタに変えたらいい」
目から鱗だった。落語を習ってみると、自分の愚痴がネタになり、聞く人が笑ってくれる。
コミュニケーションの豊かさを落語から学んだ気がした。
「やっぱり、人と話すことができる地域にしていくことだと思うんです。我々、一人一人が、人と話せる人材になっていけば、それが住み心地の良い地域になると」
現在、神栖市の14校の小学校で、吉本さんは落語を教える。落語家・神栖亭南夢明(かみすていなむみょう)として。
お寺では、地域の人でもそうでなくても、落語の稽古を無料で開放している。

落語家・神栖亭南夢明としても活動する
賽銭泥棒の面倒を見る
落語のような小咄だが、実際に起こった話だ。
お寺に賽銭泥棒が入った。
食えないのはつらい、盗んだらいつか倍にして返しなさいという思いを込めて、いつも500円を“泥棒用”に賽銭箱に入れておく吉本さんだったが、4回続いたときに、男を捕まえた。
話を聞くと、働きたいという意思はあるが、働き口がないと言った。
「やったことは悪いことだけど、放り出してもまた同じことをする」
それは吉本さん自身が育った家が裕福でなかったことも影響もしている。
「食えないっていうのは、やっぱりいちばん辛いんですよ。金持ちになりたくて賽銭盗むわけじゃない、食えなくて、賽銭泥棒というコソ泥を働く。じゃあどうすればいいのかってことです」
“毎日寺に掃除に来い、バイト代はちゃんと払うから”と言うと、男はそれから6ヶ月もの間、真面目に掃除を続けた。そして、男が就職活動を考え始めたとき、吉本さんがスーツを買った。
つい先日、男が就職が決まったと報告に来た。
本当にありがとうございました、と五千円札を吉本さんに差し出した。
「ああ、良かったなと思いましたよね。なにせ賽銭が5,000円になって返ってきましたから(笑)」
おあとがよろしいのだが、最後に、そんな住職が、移住者誘致や観光や特産品のPRを続ける神栖市を紹介しよう。
住心地の良いエリア
「農業と漁業と工業の3つの柱がしっかりしているので、市に経済力があって、住み心地が良いんですよ」
農業では、神栖市は日本一のピーマン生産量を誇る。

漁業は、黒潮と親潮がまじり合う海域のためサバやイワシなど回遊性魚が多く水揚げされ、石田丸漁業など日本有数の漁業を持つ。
工業で言えば、ご存知、鹿島工業地帯である。地元で“テイシュウ”と呼ばれる、工場の定期修理期間には、その従事者が約40万人も神栖市を訪れ、地元経済を潤している。
「でも、田舎の良さも持っていますね。人間性を感じる、ひと昔前の日本の原風景というか。花火やっても怒られませんし、私も、地域の子どもたちとドラム缶風呂やったり。自分で何でも作れる地域ですね。祭りの多い、賑やかなことが好きな土地柄なので」

写真:地域の子どもたち
落語のような暮らしを
最後に、移住を考える人にアドバイスを聞いた。
「移住を決めた人は、楽しもうと思って覚悟を決めて来られるわけだから、自分をどんどん表に出していけば良いんだと思います。その地域を自分の色に染めるくらいに」
そこで生まれる愚痴も、みんなで笑えるネタに変えて明日の活力にすること。
ぜひ、神栖市に興味が湧いた方は、恵日山長照寺の吉本住職を訪ねてほしい。
きっと落語のように、目頭を拭って笑い、膝を打ち、胸に沁みる時間が待っている。

写真:神栖亭南夢明(右端)と三遊亭圓窓(右から二番目)
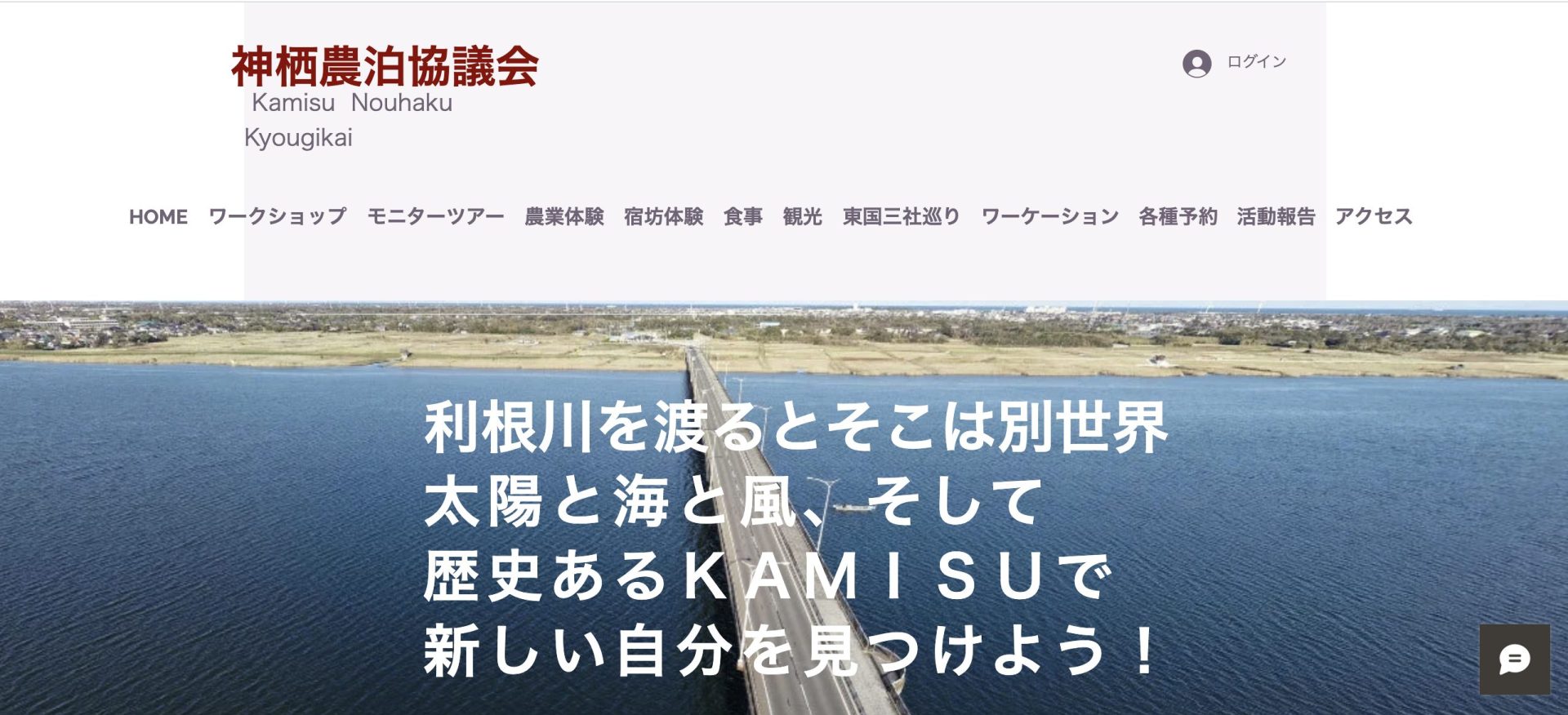
吉本さんが活動する神栖農泊協議会(かみすのうはくきょうぎかい)サイト
取材・文:槌谷昭人


















